

スマホとイラストさえあれば、いつでも・だれでも「キャラクターのライブ配信」を楽しめるアプリ『IRIAM』。開発・運営する株式会社『IRIAM』は、2021年8月に150億円の評価額をつけてDeNAグループに仲間入りしました。すでにソーシャルライブ配信サービス『Pococha』を持つDeNAと手を組むことで、サービスの成長をより一層加速させていきそうです。
そんな『IRIAM』が、「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」を策定。自らのアイデンティティと目指す未来像を力強く指し示しました。
『IRIAM』が、サービスを通してつくり上げたい世界とは? その先に見える大きな可能性とは? 生みの親のひとりで、プロダクトオーナーの真辺 昂(まなべ こう)に聞きました。
世界を見渡してもこんなに速いライブ配信は稀

早稲田大学基幹理工学部数学科中退。しばらくのフリーター期間を経て、編集者としてwebメディアの編集やIPコンテンツのメディアミックス、ゲームベンチャーの立ち上げなどを経験。2018年には、立ち上げメンバーの一人として『IRIAM』に参画し、DeNAのグループ入り後も引き続きプロダクトオーナーを務める。
ーーキャラになってリアルタイムでのライブ配信ができる『IRIAM』の仕組みに驚かされました。これはどうやってイラストを動かしているんですか?
1枚のキャライラストをアップロードするだけで、AIが自動的にモデリング(動かせるようにすること)をしてくれるんです。スマホのカメラでトラッキングした体の動きに合わせて、キャラクターの口や目などが連動して動きます。
実際にやってみると魔法のようですよ。『Preferred Networks』さんという国内最高峰の素晴らしいAI企業が開発した自動パーツ分け技術を実装していて、スマホ1台で気軽に始められる点に手応えを感じています。
ーーキャラモデルをつくるための高価な専用機材や技術も不要なのはいいですね。配信は、タイムラグを失くすことにこだわったそうですね。
「モーションライブ方式」という独自技術でつくられていて、配信のタイムラグはわずか0.1秒です。おそらく、世界を見渡してもこんなに速いライブ配信は稀だと思います。
やはり少しでも会話にタイムラグが生まれてしまうと、心の距離が生まれてしまうんですよね。たとえばテレビの中継などで、スタジオとお天気キャスターのやり取りに1〜2秒程度のラグがある光景を想像してみてほしいんですが、あれって地味なストレスを感じると思うんですよね。そうした「コミュニケーションの体験価値」には、かなり気を配ってサービスを設計しています。
人間のバイアスが取り払われ、個性が残る

ーーDeNAには、すでにリアルなライバーが顔出しでライブ配信をする『Pococha』があります。ユーザー層は被らないのでしょうか?
『IRIAM』の場合、リスナーさんに20代が多いのは大きな違いかもしれません。
僕自身も20代なんですが、あまりコミュニケーションが得意な方ではないのもあって、リアルな人と話すのは少し気恥ずかしいというか、緊張してしまうんです。それに比べて、小さな頃からアニメに慣れ親しんでいた世代というのもあって、キャラの方が圧倒的に気楽に話せるんですよね。同じことを、『IRIAM』のリスナーさんたちからもよく言われます。
ーーキャラ相手だと話しやすくなる、というのはおもしろいですね。
文字通り、キャラがはっきりしていることも大きいと思いますね。そもそも日本が独自に発達させてきたアニメーションのキャラ表現は、「その人らしさ」を抽象化するものだと思います。キャラというのは、ノイズだと思う情報量を好きなように削ぎ落とし、そのものが宿す特徴をとても魅力的に際立たせられる表現なんです。
ーーそれは逆に、「キャラになって自己表現をする」ライバーさん側にも影響があるのでしょうか?
まさにそうで、キャラになることは、人が元々秘めていた個性や才能を引き出してくれるんです。
やっぱり、私たちが現実社会で人とコミュニケーションをするときって、人種・容姿・立場・利害のような、いろんなバイアスで人を見てしまうんですよね。『IRIAM』ではそれらをまとめて「現実のフィルター」というふうに呼んでいるんですが、私たちはそうした現実のフィルターを内面化することによって、息苦しさや劣等感を感じていると思います。
こうして話している今まさに、それを感じています。読者のみなさんは良くも悪くも、僕の性別や立場や年齢などのバイアスも含めて、この記事に対する印象を決めていくと思うんです。あえてネガティブな言い方をしてみると、「男性だから(こう考えるに違いない)」「『IRIAM』社の事業部長だから(そう言えるのだ)」「20代だから(こんな意識だろう)」というふうに。そこまで極端でなくとも、そうした固定観念から完全に逃れることは難しいですよね。
『IRIAM』で「キャラになる」ということは、そうした既存の社会にある「現実のフィルター」から自由になって、もっと身軽で魅力的な自分に転生するということなんです。

ーー確かにコミュニケーションって、生まれ持った外見的な特徴などに左右されやすいですよね。
人が人に抱く価値基準って、どこまでいっても外見、経済力、フォロワー数みたいな画一的な指標の影響が強いですよね。それは人が今のような大規模な社会を営んでいる限り、逃れられないことだと思います。
ーーなるほど。『IRIAM』だと、外見も経済力もフォロワー数も関係なく、新しい自分になることができますよね。ただ、そうしたキャラクターの外見がまた新たなバイアスを生み出したりしませんか?
それについては純粋に、持って生まれたバイアスよりも、選択可能なバイアスの方が人を幸せにすると思っています。しかも、2次元キャラに対する趣味嗜好って、リアルな人に比べてとても多様で豊かなんですよ。
たとえば、TikTokなどでリアルな人にかけられるフィルターは、「美肌」「小顔」など、人を概ね同じ方向に近づけがちだと思います。けれども『IRIAM』で活躍しているキャラの見た目のバリエーションって、ツンデレ、オレ様、オネエ、ボクっ娘、妖精さん、ピエロ……と、本当に多様なあり方があるんですよ。
ーー確かに、キャラに対する好みって結構人それぞれですもんね。しかもキャラがはっきりしていると、どういうふうにコミュニケーションをとったらいいかもわかりやすくて話しやすそうですよね。
おっしゃるとおり、キャラだと最初のとっかかりが掴みやすいんですよね。しかも、まず最初にそのデフォルメがあるからこそ、そこからの見た目と中身のギャップが、コミュニケーションの中でどんどんキャラ性に組み込まれていきやすいんです。たとえば、見た目は清楚な優等生風の委員長キャラ。けれども、話してみると実はグロテスクなホラー映画が好きな一面やポンコツが露見していく……というように。
そんなふうに、最初は典型的なキャラ設定だったのが、リスナーさんとのコミュニケーションの中でどんどん唯一無二なキャラに育っていく例を何度も見ました。こうしたコミュニティにおけるオリジナルなキャラの深まり方は、『IRIAM』のおもしろいところだと思います。
ーー外見その他のなにがしかにしばられずコミュニケーションができて、そこにオリジナルなコミュニティが育っていく。最初はニッチな市場かと勘違いしましたが、思いのほか、社会的な意義や価値が高いサービスですね。
少なくとも私たちは、キャラであることを、単にニッチなジャンルだというふうには思っていません。誰しもが顔出しで気持ちよく配信できるわけではないですし、ここまで述べてきたように、キャラの方が互いのコミュニケーション価値が高い。それは、いわゆるオタク層と言われる人たちのみに留まらない、人にとって非常に本質的な価値だと思っています。
そんなことを考えるきっかけになったエピソードがあります。2018年に『IRIAM』を起ち上げてまだ間もない頃に、今回のミッションを考える上でも、忘れられない瞬間がありました。
最初の配信で大号泣!?

ーー忘れられない瞬間とは?
リリースした当初って、ライバーさんの数が圧倒的に足りないんですよね。だからいろんな専門学校などに営業に行って、「生徒さんに配信をさせてみてほしい」と泥臭く声をかけたりしていました。
その中で、ライバーに挑戦してくれるという声優の卵の方と出会いました。40代後半で声優の夢をあきらめきれずに頑張っている方で、面談をすることになったんです。けれども、その方は極度のあがり症で、緊張のあまりボロボロと泣き出してしまって、ほとんど話もできないままにその面談は終わってしまったんです。
正直、その場では面食らってしまって……「配信を無事にできるかな」と心配でした。
ーーその方に『IRIAM』のライバーをしてもらったと。実際どうでした?
初配信では緊張で大号泣していました。やっていることは面談のときとまったく同じです。けれども、キャラと声という情報だけになるとすごく健気でかわいらしくて……純粋な応援の気持ちがその場に湧き上がったんです。すぐさまリスナーさんたちが集まって「大丈夫?」「なんで泣いているの?」と温かい声をかけあって、みんなで支え合うような雰囲気になりました。
ーー同じ大号泣でも、リアルな人間とキャラで印象が変わったんですね。
ええ。配信後、その方が言っていたことが今でも忘れられません。その方は泣きながらこう言ったんです。「生まれて初めて、自分の声をかわいいと褒めてもらえた」と。
その言葉を聞いた瞬間に、『IRIAM』の持っているポテンシャルを実感しました。このサービスは、なにか自己表現をしたいという気持ちがあって、人としての魅力もあって、けれども「現実のフィルター」に邪魔をされてそれがうまく出せなかった人たちのためのものなんだと。そしてそういう人は、いわゆるオタク層に限らず、本当にたくさんいるはずだと。
思えば、インターネットのUGC(User Generated Contents=ユーザー生成コンテンツ)の文化は、常に既得権益を民主化してきました。テレビ・ラジオ・出版が第四の権力と呼ばれていたような時代から、象徴的にいえばYouTubeはテレビを、Twitterはラジオを、ブログは出版を民主化させてきたように思います。『IRIAM』は、現実のフィルターという強い価値観を取り払ったフェアな世界で、しかも「雑談」という本当に誰でもできる自己表現をもとにしたUGCなので、非常に大きなポテンシャルを秘めていると考えています。

ーー「民主化」の言葉が象徴的ですが、そもそも初期のインターネットには個と個をつなぎ合わせて、あたらしい紐帯の形をつくるのだというような幻想がありましたよね。
そうした夢を信じることができたのも、SNSが大衆化するまでだったような印象ですよね。
先進国では近代以後、息苦しいムラ社会を嫌って、都市化や消費文化の中で個人主義的なあり方を推し進めてきました。それ自体は素晴らしい達成だと思うのですが、そのカウンターとして人の孤独化も進んでいて、今や「孤独は現代で最大の公衆衛生上の課題」とまで言われるようになっているんです。そんな中でも、インターネットの登場は現実社会で孤独を感じている人たちの居場所という側面があったはずですが、その後のSNSの大衆化はむしろ孤独を加速させていったと思います。
僕はこれを、ビジネスモデルと非同期コミュニケーションの問題だと考えています。SNSの広告モデルは、絶えず人の注意を引き続けるためのアルゴリズムを非常に高度に発達させてきました。その最適化のひとつが、たとえば「自分だけみんなから取り残されてないか」「自分はみんなに比べて劣っているんじゃないか」というような、人間関係上の不安をそれとなく煽る手法だったと思います。
そしてそれに拍車をかけているのが、非同期コミュニケーションです。人は言語の発達によって複数のコミュニティとゆるく非同期的に関われるように進化してきた一方で、脳はどこまでいっても「いま目の前にいる人」のことを信頼するようにできている。非同期なネットワークの中ではどうしても不安や不信が漂いやすくて、だからこそ私たちは日々「既読無視されたかも……」とか「このいいねってどういう意味?」みたいな深読みをして繊細に思い悩んだりしているのだと思います。
『IRIAM』のコミュニティ体験は、それとは異なる温かなものです。ビジネスモデルから導かれる私たちのアルゴリズムは、ユーザーさんにより深いコミュニティ体験をしてもらう方向に発達させていくことができます。そして常に顔が見える距離感で、それこそ数カ月から何年という単位で同じ時間を過ごしあうファンコミュニティのあり方は、強い心理的安全性があります。私たちが育んでいきたいのは、そうした強いつながりのコミュニティの文化なのです。
ーー『IRIAM』が受け入れられる時代背景がよくわかりました。そうした孤独感は、グローバルでも共通する課題かもしれませんね。
ええ。そして、イラストはどの国でも通用する共通言語になるので、展開する国が増えれば、生まれるイラストの経済圏もより広がっていく可能性があると考えています。ライブストリーミング自体は中国発ですが、アニメ・キャラ文化は日本が独自に発達させてきた歴史があるので、それらが持つ可能性を日本発のユニークなプラットフォームとして世界に広めていけたらいいなと思っています。
深い世界観と目指す未来を言語化したMVV

ーー今日お話いただいたような設計思想を踏まえた『IRIAM』のMVV(ミッション・バリュー・ビジョン)をつくられたそうですね。
はい『IRIAM』に込められた想いや私たちのアイデンティティを、あらためてきちんと言語化することで、皆で同じ方向を見て歩んでいきたいと思って作成しました。かいつまんで紹介させてください。
ーーミッションは『心でつながる魔法をかける』です。どういう意味でしょうか?
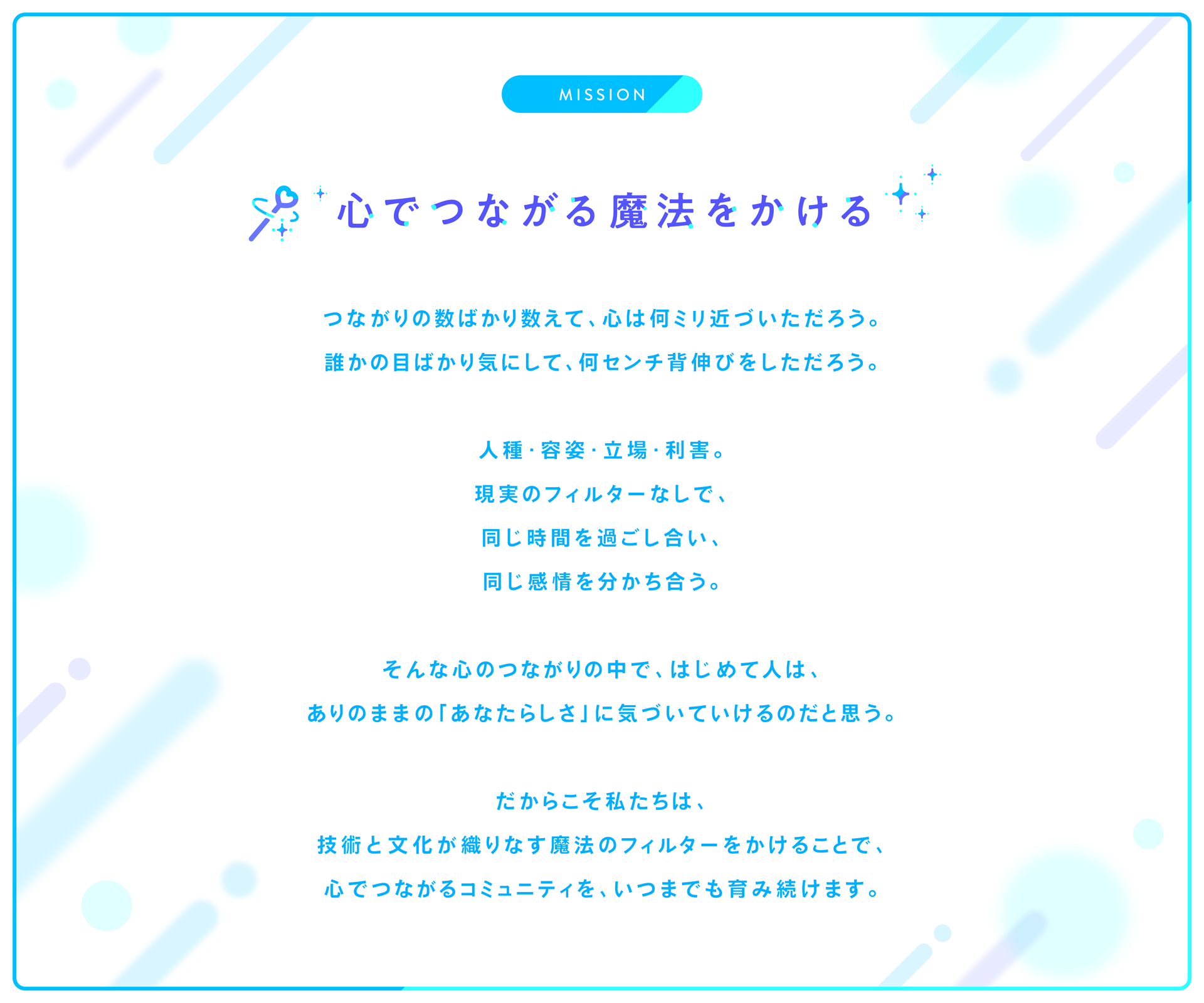
私たちはつながりの量ではなく質(心のつながり)を大事にするんだということ、そのために同じ時間・同じ感情を分かち合うベースの体験に加え、「現実のフィルター」の代わりにさまざまな「魔法のフィルター」をかけていくんだ、ということが書かれています。
ここでの魔法は、ラグのない通信や、キャラになる技術のことだけではありません。ここでは深堀りしませんが、私たちはコミュニティの文化が人をかたちづくっていくのだと考えていて、文化もまた非常に重要視している要素です。
ーー次に掲げたビジョンが「心のつながりが集い合う新たな文化の共創」です。

ビジョンとしては新しいUGCの文化を共創していくことを目指しています。僕はあらゆる新しい文化というものは、最初はいかがわしくて、みくびられやすいものだと思っていて。たとえばYouTuberも出てきた当初は世間からひややかな視線を浴びていましたが、今や子どものなりたい職業ランキングのトップに輝いている。そしてそうしたUGCプラットフォームの文化は、世界の価値観に大きな影響を与えていると思います。
僕らが信じている『IRIAM』の文化も、今はまだその価値観を知ってもらえていないものだと思っています。けれども、その『IRIAM』の文化を育てて世界を覆っていくことで、「現実のフィルター」で満ちたこの世界の価値基準を少しでも変えていけたらと思っています。そして最終的には、この日本発の文化をきちんとしたかたちで文化史に残していきたい。
ーーそしてバリューは「コミュニティファースト」「プルス・ウルトラ」「ブループリント」の3つ。どれも『IRIAM』らしいですね。
これらのバリューは、すべて『IRIAM』内で培ってきた「コミュニティ論」をもとにつくられました。最初の「コミュニティファースト」はコミュニティが大事というものではなくて、「コミュニティを出発点にする」という意味です。というのも、『IRIAM』はあくまでプラットフォーマーなので、主役は運営ではなくコミュニティなんです。私たちはあくまでも、そのコミュニティの火種を育てるために、薪をくべ風を送る存在なのだということを強調するバリューです。
「プルス・ウルトラ」はスペインの国旗のシンボルにもなっているラテン語の合言葉から拝借しました。ローマ神話の中で世界の限界を示す柱に刻まれていた「この先には何もない(Non Plus Ultra)」という言葉を、むしろ「この柱を限界ではなく、新世界への入口だと思って乗り越えよう」と前向きに捉え直したことに由来しています。全員が一丸となってチームの期待を超え合う相乗効果によって、チームというコミュニティの熱量をあげていこうという意味のバリューです。
最後の「ブループリント」は、日本語では青写真といって、未来の設計図のことを意味しています。コミュニティというものは、気をつけないと現状維持を望んで、ゆるやかに衰退してしまう性質を持っていると思うんです。だからこそ、長期的な青写真をきちんと描いて、たとえ一時的にネガティブがあったとしても、よりコミュニティにとっていい未来に向けて変化させていこうという想いを込めたバリューです。
ーーMVVを作って、変化を感じることはありますか?
「MVVに沿っているか?」という視点や、コミュニティに関する議論がより活発になりました。うちのメンバーは『IRIAM』のことが大好きな人がたくさんいて、『IRIAM』という場に寄り集まっているひとつひとつのコミュニティを心から大事にしています。コミュニティは極めて複雑で難しいものだと思うのですが、そこに対してうちのチームが磨き込んできた知見は、他の会社には負ける気がしません。改めて、そのことを今回MVVというかたちにできて良かったと思います。
多種多様なポジションで採用強化中!

ーー今後、どのような人にジョインしてほしいですか?
なによりも、『IRIAM』のMVVに共感してくれる人です。そのことをとても重要視していますね。2次元文化に親しみがある方が望ましいですが、どちらかというと、コミュニティや新しい文化に関心がある人の方が会社のカルチャーには合っていると思います。今は事業の拡大に人材が追いついてなくて、数年で500名くらい採用したい気持ちです(笑)。
職種も多種多様なポジションを募集しています。サービスの急拡大に対応できるオペレーション強化の開発、ライバー文化のブランディング、イベントの設計、配信内コミュニケーションのデザイン、toB分野の事業開発、コミュニティマネジメント……などなど、たくさんありますが、特にエンジニアさんの仲間を積極的に探しています。
『IRIAM』というサービス名は、「MIRAI(未来)」のアナグラムからつけられたものなんですが、そんな新しい文化の未来を一緒につくりたいという人が参画してくれることを楽しみにしています!
※本記事掲載の情報は、公開日時点のものです。
※本インタビュー・撮影は、政府公表のガイドラインに基づいた新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインに沿って実施しています。
聞き手:箱田 高樹 執筆:日下部 沙織 編集:フルスイング編集部 撮影:小堀 将生