データホライゾンの躍進を支える、種苗メーカー出身営業パーソンの流儀
2025.03.05

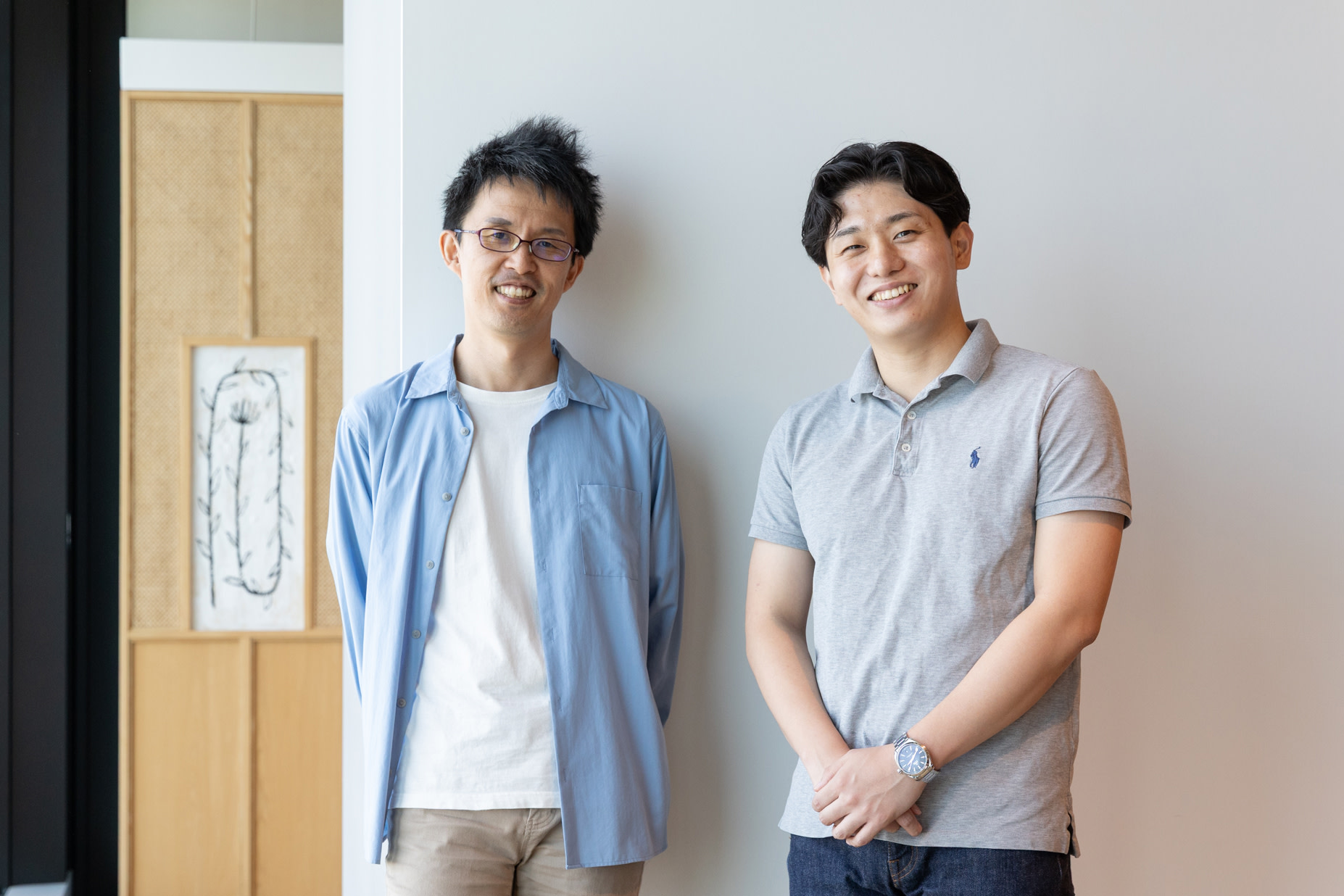
「全社員がAIを徹底的に使いこなし、生産性を倍に、あらゆる業務を 『AIネイティブ』につくり変える。」
DeNAグループ全体でAIネイティブカンパニーへの変革が進む中、データヘルス関連サービスを提供するデータホライゾン社(以下、データホライゾン)では、現在「AI活用の日常化」に向けた3つの取り組みが進行中です。
本記事では、データホライゾンが取り組む「AIオールイン」の舞台裏を、「ビジョン編」と「実践編」の2部構成でご紹介します。
前編となる今回は、データホライゾンCTOの伊藤 康太郎(いとう こうたろう)とDeSCヘルスケア事業コーディネーション・マネジメント室の松下 祐斐(まつした ゆうひ)に、AI戦略の全体像とその根底にあるビジョンについて詳しく聞きました。
目次
──今年5月の経営方針発表での「データホライゾン(DH)もAIにオールイン」宣言、8月の「DH AI Day」の開催、そして全国の拠点を巡業しながらのAIイベント実施など、組織の大変革に「今」踏み切ったのはなぜですか。
伊藤 康太郎(以下、伊藤):なぜ「今」なのか、という話の前に、AIの時代をどう見るかというところからお話しさせてください。
AI、特に生成AIは、インターネット、スマートフォンに続く第三の不可避かつ不可逆的な波だと捉えています。AIは今後あらゆる業務シーンに組み込まれ、テクノロジーとオペレーションはもはや切り離せません。AIを徹底的に使いこなし、創造的思考を持てる「スマートクリエイティブ」が競争優位の源泉となるこれからにおいて、社会や産業関係なく、あらゆる業務において根本的な変革が必要となります。
AI分野における著名人の一人、Dr. Andrew Ng の“AI is the New Electricity”という言葉の通り、産業構造そのものが10年でガラリと変わるでしょう。非常に抽象的な話になりますが、CTOとして技術が経営にどう影響を与えるか、会社が5年後、10年後にどうなっていくべきかを常に考える中で、AI活用を今進めることが会社の未来をつくることにつながると考えました。
──特に「AI」が今後の事業成長、そして組織変革の鍵になると考えた理由は何でしょうか。
伊藤:データホライゾンが「持続的かつ構造的な成長」という大きな目標を達成するためには、日々の業務のあり方を根本から見直し、従業員一人ひとりが持つ力を最大限に価値ある仕事へと振り向かせる必要があります。その最大の鍵となるのがAIです。
AI活用によって日々の「単調な作業」や「繰り返し作業」といった業務を効率化し、会社の価値創造に直結する「顧客と向き合う時間」や「新しいアイデアを生み出す時間」をつくり出す。そして従業員みんなにこれまで以上に仕事に「ワクワク」してもらい、会社全体の成長を加速させていこうと考えました。
──それは、多くの従業員の方々が単調な作業や繰り返しの作業に追われていたということでしょうか。
伊藤:はい。当社は現在データヘルスサービスを通じて全国に600を超える自治体様とのお取引があり、1自治体あたり複数の事業実施があるため、見積もりの数だけでも年間1,000件を超えます。
個別最適化されたオペレーションを回すには人も時間もかかります。社員からも「単調な作業や繰り返し作業が多くて、創造的な仕事ができていない」という声が上がっており、こうした課題に対して、AIはうまくハマるだろうという直感がありました。
──とはいえ、新しい変化に対して、社内から反発はなかったでしょうか?
伊藤:ありませんでした。幸い、経営陣も社長をはじめとしてテクノロジーや新しいものが好きなカルチャーがあり、変化を柔軟に受け入れる土壌があります。創業者である内海会長も非常に先見性があり、「これをやろう!」とトップダウンで新しいことに挑戦するのに慣れている社風がありました。
──宣言が出た当初、現場の皆さんの反応はいかがでしたか?
松下 祐斐(以下、松下):最初は「開発部門が中心に使っていくのだろう」という雰囲気でした。それ以外の部門では、議事録作成のような手のかかる業務の一部をAIを活用して効率化していくのだろうと考える人も少なくなかったと思います。
しかし、まもなくCTO直轄のAI CoE(AI Center of Excelence)チームが立ち上がり、各部門のAI推進担当と連携しながら全社横断での取り組みがスタートしました。経営層が現場に出向いて直にメッセージを伝えたり、AI CoEチームがAI活用の成功事例を積極的に発信してくれたり、会社の本気度が伝わってきましたね。伝えられる情報をベースに「こういう使い方ができるのか」「あの人にできるなら自分にもできるかもしれない」と、自分ごととして捉えるきっかけになりました。
──ちなみに、全社的な取り組みを進める上で、壁となったものはありましたか?
松下:正直、部門間の温度差はあったと思います。開発部門や営業部のように率先して使っていこうという部署がある一方で、仕事柄や年齢層の違いから「自分には関係ないかな」と少し及び腰になってしまう方もいらっしゃったと思います。けれど、マネージャー陣総動員で現場を回って実際にやってみせることが、会社全体の意識につながっていったのだと思います。
──実際、「AIオールイン」をどのように進めているのでしょうか。
伊藤:AIの活用は、大きく「生産性の向上」と「AIを使った新しい価値の創造」の2つに分けられますが、いずれにしても、ものの考え方自体を変えて業務の前提や発想を根本から変える必要があります。生産性を上げるためにAIを使おうとしても、「自分の会議の議事録だけ楽になればいい」といった個人的な改善に留まっていては、生産性2倍という目標には到底到達しません。
AIを本当の意味で使いこなすには、業務プロセスの中にAIを組み込み、そのAIが処理しやすいようにインプットとアウトプットを設計し直す、「AIネイティブ」なオペレーションに組み替える必要があります。ですから、AIによる生産性の改革は、組織改革そのものだと考えていました。
──具体的にどのようにAIを組み込んでいったのでしょうか。
伊藤:まず「AI活用の日常化」に向けて、3つの指針を設けました。
──1. の「ビジョンと危機意識の共有」にある「現場目線」というのは?
伊藤:最初に、5月に開催した経営方針発表会で、全社員に向けて「この波に乗らなければ、5年後、10年後に会社としての仕事がなくなってしまうかもしれない」と、かなり強いメッセージを発信したように記憶しています。その上で「なぜ今AI活用を進めて変わらなければならないか」という理由を浸透させるのは、現場目線で語ることが不可欠でした。
現場目線とは、社内の多くの社員が「面倒だ」と感じている作業、たとえば「前年度と今年度の契約書の比較」「政府が発行する膨大なレポートからの有用な情報抽出」「資料探し」といったものから、会議の調整や議事録作成まで。いずれも重要かつ欠かせない定型業務ではあるものの、数が積み上がってくると創造的な業務を圧迫する要因になります。
そこで、「そうした課題は、AIを活用すれば解決できますよ」と。まずは「議事録作成」と「調査」と言う2つの基本業務を全社員がAIを使ってできるように共通の「型」を示しました。
松下:使うツールは全社で標準導入しているGoogle WorkspacesのGemini、Google Meet、NotebookLMの3つ。そして、「議事録の作成」と「自分で調べたいことを調べる」という2つの基本動作を全社員ができるように、というところからスタートしました。この「型」を覚えたことで、次への応用と言いますか「もっと使ってみよう」「こんな使い方もできるんじゃないか」という動きが加速したように思います。
──2. の「AI CoEモデルによる推進体制」については、どのように体制構築したのでしょうか。
伊藤:AIに対する熱量の高い人が個の熱量と突破力で推進したり、有志が集まってボトムアップで草の根活動を展開することももちろん大切ですが、継続的な取り組みとしてスケールさせていくためには、まとまったリソースや部門間の情報連携、明確なガイダンスといった組織としての体制を用意することが必要でした。
エンジニアやビジネス職の横断部門のリーダーでCTO直轄のAI CoE コアチームを形成し、各部門からAI推進の旗振り役としてAI推進者を任命。部門のAIニーズやアイデアを収集・共有してもらいながら情報の連携と基盤を整備していきました。
──ヘルスケア領域では人の身体や疾患データなど機微な情報を扱うので、AI活用の倫理面や安全面には特に配慮が必要かと思います。具体的にどのようなガイドラインを設けられたのでしょうか。
伊藤:おっしゃる通り、全社のガイドラインの策定には、「ガードレールを徹底する」ことが絶対条件でした。「ここまでは確実に大丈夫、この一歩先はダメ」という線引きをした上でデザインしています。
実は、1年ほど前からデータホライゾンでも一部のAIツール利用は可能にしており、社内で「こういう範囲なら使ってもよい」という線引きは進めていました。ですので、この大変革におけるある程度の下地はありました。
──ガイドラインを作成する上で、法務やセキュリティ部門など、部署を横断した連携で苦労した点はありましたか?
伊藤:法務部門やセキュリティ部門との連携で、そこまで大変だったという印象はありません。というのも、DeNAの担当部署がかなりしっかりとしたレールを敷いてくれていたので、私たちはそれに乗っかれば良かったという側面が大きいです。もちろん、それを当社の文脈に照らし合わせて判断する必要はありましたが、基盤があったのは助かりました。
また、データホライゾン内にも独自のセキュリティ・リスク管理部門があり、常日頃から密にコミュニケーションを取っていたこともスムーズに進んだ要因だと思います。
──そして、3. の「ホットスポットの発見と展開」について。これは1つ目の「ビジョンと危機意識の共有」にもつながるイメージがありますが、各所で見つけるというのは実際どんな動きをされているのですか?
松下:マネジメント層が「全拠点に直接行きます」と宣言し、マネージャー陣で分担しながら、全国を巡業するワークショップを企画しました。全国の拠点を巻き込んでいく「スカウトキャラバン」のイメージです。目指すべき抽象的なゴールは伝えつつ、最初の一歩として具体的に何をするかをマネージャー等が示す。伊藤さんも実際に訪問されていますよね。
伊藤:私が実際に訪問したのは東京、広島ですね。リモートでもできなくはないですが、本気度は伝わりにくい。「ここまで本気でやるのか」と感じてもらうためには、直接現地に行って顔を合わせることに意味があると思いました。
松下:当社のマネージャー陣は、一人ひとりの個性や性格をよく理解している方が多いと感じます。このAIの取り組みに関しても、ただ「やっておいて」と指示を出すのではなく、「自分はこう考えている」と示した上で「この人にはどう言えばやる気になってくれるか」というモチベーションの火種を理解し、相手に合わせた伝え方をしてくれる。
私自身も、具体的な手順に落とし込んでもらったことで「これなら自分にもできるかもしれない」とマインドチェンジが起きました。抽象的な話ではなく、マネージャー陣の「チームの中でAIをどう活用していくか」の熱量のある語りかけも大きかったですね。
──変革のキーパーソンとなるメンバーを各拠点でどのように発掘しているのでしょうか。
伊藤:私たちは変革のキーパーソンを「ヒーロー」と呼んでいて、各部署のマネージャーに「自主的に動いていて、温度感の高い人はいないか」とヒアリングし、紹介してもらった人たちに直接話を聞きに行く、という形で見つけています。
松下:伊藤さんが描いてくれた全体像を元に、各部署との細やかな連携や具体的な計画をどう動かしていくかという現場寄りのコーディネーションが私の役割ですね。
──「ヒーロー」ですか?そんなふうに言われると、気持ちが上がります(笑)。
松下:たとえば、ある営業担当者がAIレコーダーを実験的に導入し、半日かかっていた議事録作成を30分で終えられるようにしたとします。それは営業部門全体の生産性を上げた「ヒーロー」です。
そうしたヒーローたちの成功事例を積極的に展開し、このAI活用のブームを一過性のものに終わらせず、継続的に盛り上げていくための燃料のような存在であり続ける。成功事例を持つ方々、すなわち次のヒーローを生み出せるように、芋づる式に成功者が増えていく仕組みをつくりアップデートしていくのが今後の私のテーマですね。
──実際に開催されたワークショップでの、参加者の反応はいかがですか?
松下:印象的だったのは、質疑応答の時間になると、こちらが用意していた想定問答が必要ないほどに参加者から積極的に手が挙がったことです。「分からない」ことを恥ずかしがらずに質問できる雰囲気があり、広島では開催後も伊藤さんが10人くらいに囲まれて質問攻めにあっていました。
伊藤:ある社員は、AIを使って部署にあったテンプレートファイルを9割削減できたそうです。「今まで自分ができなかったことができるようになった」ことに、ものすごくワクワクしていると話してくれました。こうした「自分の手で改革を成し遂げた」という成功体験をどんどん見つけていきたいですね。
「生産性倍増」「従業員のワクワク」。この2つを両立させるべく、データホライゾンが投じた一手は「AIオールイン」でした。前編では、その背景にあった経営陣の強い危機感と、単なるツール導入に終わらない全社的なムーブメントをいかにして巻き起こそうとしているのか、その戦略の骨子が語られました。
続く後編では、トップダウンの号令と、それに応えるボトムアップの活動がどのようにして全社的なうねりになっていったのか。現場で生まれた「ヒーロー」たちの活躍を通し、この変革がもたらしたリアルな成果を追います。
※本記事掲載の情報は、公開日時点のものです。
執筆・編集:川越 ゆき 撮影:小堀 将生
撮影場所:WeWork 渋谷スクランブルスクエア 共用エリア/会議室
DeNAでわたしたちと一緒に働きませんか?